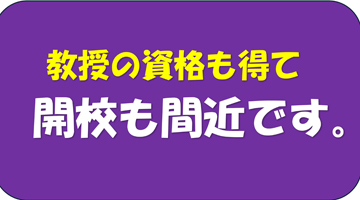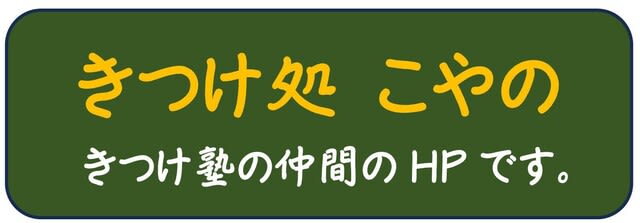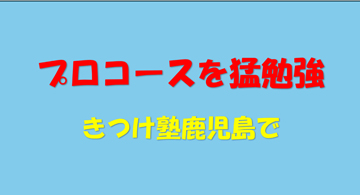教授の資格得て、「着付け文化」担う一翼に
昨年の、「全日本きもの文化研究協会」主催の認定式で、着付けの教授を取得した堤先生。
地元、都城を中心に「きものの着付け教室」開校を決意されました。
以来、今後教えていく着付け講師としての技術と、教室経営の心構えを学ぶことになります。
今日の堤先生の、養成コースの今日の課題は、
●「伊達衿をつけた附け下げ」に、「二重太鼓の自装」。
●「手結びのお文庫」。
二つの課題とも、手早く仕上げられました。
開校間近の、教室通信でした。(通信者◇木下先生)

 舞踊の着付けを、見学なさいませんか❣
舞踊の着付けを、見学なさいませんか❣
このブログをご覧のみなさん、関心があったら講座見学にお越しになりませんか。
下記のお電話でお問合せください。
きっとあなたの関心にお応えできるものと思っています。
時代物の着付けは、歴史の楽しいお勉強講座です。
講座見学のお問合せは、
090‐4489‐9745 担当者 市来まで。
#訪問着付け #日本舞踊着付け #衣裳方#舞台のメイク #振袖の着付け #花嫁の着付け #美容師の着付け #演劇 #ファッシヨン

#訪問着付け #日本舞踊着付け #衣裳方#舞台のメイク #振袖の着付け #花嫁の着付け #美容師の着付け #演劇 #ファッシヨン
#訪問着付け #日本舞踊着付け #衣裳方#舞台のメイク #振袖の着付け #花嫁の着付け #美容師の着付け #演劇 #ファッシヨン