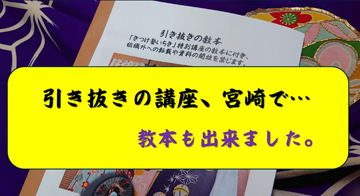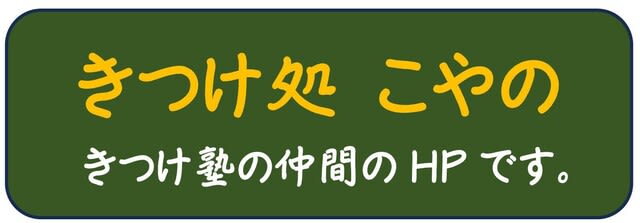本番の時はドキドキ、早変わりの着付けです。
宮崎の「きつけ塾いちき」では、歌舞伎や日本舞踊などでみられる「早変わり」の着付けを学びました。
日本舞踊の演目、「手習い子」の衣裳を使って、着付けの準備。
引き抜きというのは、一番最初に着込む衣裳の上に、さらに「かぶせ」と言われる、もう一枚の衣裳を重ねて着せます。(もちろん二枚の衣裳は、色・柄ともに違ったものです。)
この二枚の衣裳が、かぶせてある衣裳一枚に見えるように、少し太めの絹の糸でつないでいきます。
一般に裾引きの場合は、長・短、二本の絹糸を「一対の玉」につなぎ、合計八つの玉・16本の絹糸で縫い込み、準備は完了です。
宮崎では、福森さんと釜付さん、二人の衣裳方が、特訓でお稽古致しました。
引き抜きの準備に時間をかけて、着せて引き抜くのは瞬間のワザ。
ナスコンの衣裳が水色の衣裳に早変わり。お稽古が成功した瞬間です。
「きつけ塾いちき」では、一つの舞踊の会で、8人の早変わりをした経験があります。
リハーサルで引き抜いた衣裳は、あくる日に向けて、8人分を縫い直して本番に備えます。
引き抜きのお仕事は瞬間ですが、準備にはかなりかかります。
早変わりが成功すると、観客のどよめきと歓声が聞こえます。
衣裳方としてはやりがいを感じる瞬間です。
失敗はしていませんが、本番の時はドキドキです。
みなさんお疲れさまでした。
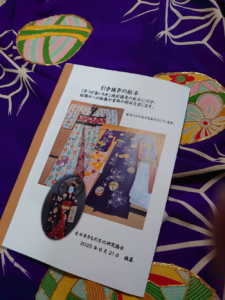 テキスト
テキスト
 準備
準備
 引き抜きを着付け
引き抜きを着付け

引き抜いた時の写真(上の写真→広島講座で)

舞踊の着付けを、見学なさいませんか❣
このブログをご覧のみなさん、関心があったら講座見学にお越しになりませんか。
下記のお電話でお問合せください。
きっとあなたの関心にお応えできるものと思っています。
時代物の着付けは、歴史の楽しいお勉強講座です。
講座見学のお問合せは、
090‐4489‐9745 担当者 市来まで。
#訪問着付け #日本舞踊着付け #衣裳方#舞台のメイク #振袖の着付け #花嫁の着付け #美容師の着付け #演劇 #ファッシヨン